こんにちは。shunです。
ベースのピック弾き――一見シンプルに見えて、実はとても奥が深い奏法です。
指弾きとは違い、ピックの角度や握り方、アタックの強さで音の印象が大きく変わります。
今回は、ピック弾きを上達させるための具体的な練習法と意識すべきポイントを解説していきます。
ピック弾きの魅力と難しさ
ピック弾きの魅力は、何といっても「アタック感」と「抜けの良さ」。
ロックやパンク、メタルなど、バンドサウンドにしっかり存在感を出すにはピック弾きが最適です。
一方で、弦ごとの音量差やノイズが出やすく、慣れないうちは安定したリズムを保つのが難しいという課題もあります。
ピックの持ち方を見直そう
まず大切なのはピックの握り方です。
強く握りすぎると手首が固まり、弾きにくくなります。逆に緩すぎるとピックがずれてしまう。
理想は「弾いた瞬間に少ししなる程度」の力加減です。
また、ピックを当てる角度も重要。
弦に対して少し斜め(30〜45度)に当てると、滑らかに弾けてノイズも減ります。
真っ直ぐ当てると力強い音になりますが、引っかかりやすくなるので、場面によって使い分けましょう。
手首の使い方を意識する
ピック弾きが上達しない人の多くは、腕全体で弾いてしまう傾向があります。
実際は、肘から先をあまり動かさず、手首のスナップを中心に使うのがポイントです。
手首をリラックスさせ、軽く振るようにしてピッキングすることで、スピードも安定感も上がります。
この動きを身につけるには、メトロノームを使って8分音符・16分音符を一定に刻む練習が効果的です。
ダウンピッキングとオルタネイトの使い分け
速い曲を弾くには、ダウンピッキングだけでは限界があります。
オルタネイト(ダウン→アップの交互ピッキング)を使うことで、長時間安定して弾けるようになります。
しかし、音の粒立ちが変わるため、曲によってはダウンピッキングだけで統一した方が良い場合も。
両方の奏法を身につけ、**「音の一貫性」と「体力のバランス」**を考えて選択するのが理想です。
弦移動の精度を高める練習法
ピック弾きの最大の難関が「弦移動」です。
弦をまたぐ瞬間にタイミングがずれてしまう人は多いですが、これを克服するコツはゆっくり正確に。
最初はテンポ60くらいで、
4弦→3弦→2弦→1弦→2弦→3弦→4弦
という往復練習をメトロノームに合わせて繰り返します。
徐々にテンポを上げていけば、安定感が自然に身につきます。
音作りも練習の一部に
ピック弾きは音の出方が大きく変わるため、EQやピックアップのバランス調整も重要です。
中域(ミッド)を少し上げると、アタックが抜けやすくなり、ピック特有の「カチッ」とした音が際立ちます。
逆に、低音を強めると「太く力強いロックベース」の印象に変わります。
音作りを工夫することで、練習のモチベーションも上がります。
まとめ:ピック弾きは「力ではなくコントロール」
ピック弾きを上達させる鍵は、力を抜いて正確にコントロールすることです。
強く弾くのではなく、「必要な力だけを使う」ことを意識するだけで音は見違えるように変わります。
焦らず丁寧に練習を重ね、自分らしいピッキングスタイルを確立していきましょう。
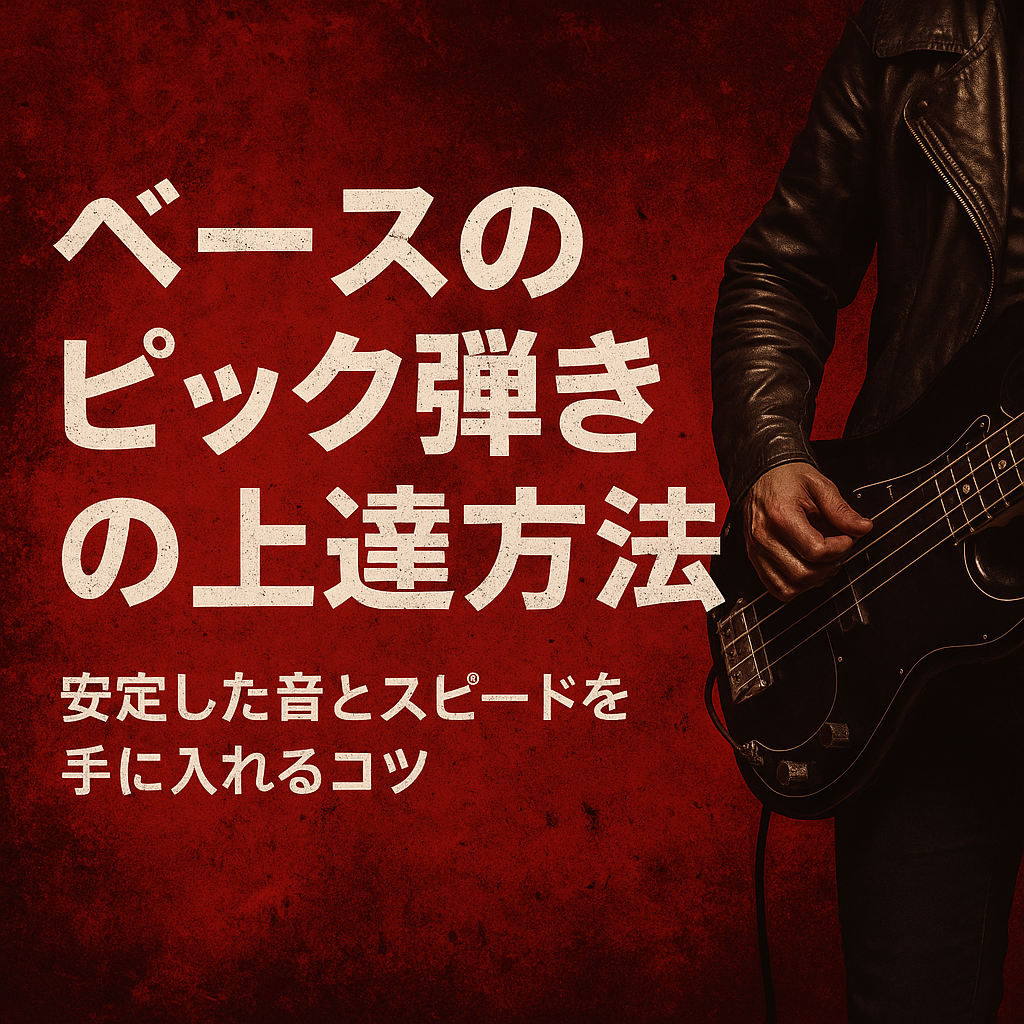


コメント