こんにちは、shunです。
今回は、僕自身のベース人生を振り返りながら「初心者からどう成長していったのか」をまとめてみます。これからベースを始める方や、伸び悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
ベース初心者1年目|リズム感を意識せずに音源に合わせるだけの日々
13歳。ベースを始めた最初の1年間は、とにかく「音を出せるだけで楽しい!」という気持ちで弾いていました。
リズム感やグルーヴなんて分からず、好きな曲に合わせてただ同じ音を弾くことに夢中。今振り返ると音はズレていても、当時は「弾けてる気分」になれていたんです。
⇒ ベース初心者によくある「リズムを考えずに弾いてしまう」という経験は、僕も例外ではありませんでした。
2年目からの変化|スラップ奏法やテクニックへの挑戦
2年目に入ると、「もっと上手くなりたい!」という欲が出てきました。割とみんなが通る道だと思いますが、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(レッチリ)。
フリーのスラッププレイに憧れて、ストラップを下げてひたすら練習しました。最初はノイズばかりでしたが、少しずつ形になってくると「技術を追いかける楽しさ」を実感できました。
僕自身指弾きから入りましたが、この時期からピック弾きも取り入れてオルタネイトピッキング、弦飛ばしでピックを弾くなどJanne Da Arcの楽曲をひたすら弾きこんでアップピッキングのぎこちなさを克服しました。
この時期にスラップやピック弾きを練習したことが、後のバンド活動でも大きな武器になりました。
また、同時期にギターを練習していた事もあり、ベースがメインでありながらもピックを使うという事を意識して練習していた事も、今に繋がっているのかな?と思います。
3年目以降|バンド活動で学んだ「ドラムを聴くこと」の大切さ
3年目からはバンドを組み、本格的に人と合わせる経験が増えました。ここで初めて「ベースは単独で弾くだけじゃない」と気付かされます。
特に意識するようになったのはドラムとの関係性。
- キックに合わせて低音を支えること
- ハイハットのリズムを感じ取ること
- リズムの「タテ」を揃えること
この感覚を掴むことで、バンド全体の音がまとまることを実感しました。
また、裏のリズムを意識してメトロノームで弾き込むなんてこともやっていました。
バンドで人間が叩くリズムの揺れを感じるのも、1つの楽しみ方ですね。
現在|音楽全体を意識しながら臨機応変に対応する
バンド活動を続けていく中で、次第に「自分の音をどう出すか」に意識が移りました。
- ベースの音を前に出すか、沈めるかを場面ごとに判断する
- 他の楽器との音量・リズムバランスを調整する
- ライブで瞬時に対応する柔軟さを持つ
こうした意識が芽生えてから、演奏に奥行きが出てきたと感じます。単に弾くだけではなく、「音楽を作る一員としてどう動くか」を考えるようになったのです。
また、耳を鍛える。作曲をする。頭に理屈を叩き込む。理屈では説明できない感覚を覚える。こういったベースだけではないクリエイターの要素も本当に音楽を楽しむ上では大切なことなのかもしれないですね。
まとめ|ベース人生は積み重ねで作られる
振り返ると、
- 1年目は音を出すだけで楽しかった時期
- 2年目はスラップなど技術に挑戦した時期
- 3年目以降はバンドでドラムを聴き、音楽全体を意識するようになった時期
この積み重ねが、今の僕のベーススタイルを作ってきました。
これからベースを始める人も、「弾けない」「リズムが合わない」と悩むのは当たり前。大切なのは、その段階を楽しみながら一歩ずつ成長していくことだと思います。
僕のベース人生は色んな人が関わってくれて、色んな経験が出来て、今も成長中です。
なにより大切なことは、立ち向かうこと。
折角お声かけ頂いたことは、やれると思ったら分かりました。の二つ返事でやり遂げる。
チャンスを無駄にしない。
その中で末永く続けていける事がなにより良いことなのかもしれませんね。

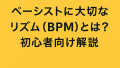
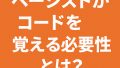
コメント