こんにちは。shunです。
ベースを練習していると、「家で弾いた時は良い音だったのに、スタジオやライブでバンドと合わせると全然違う!」と感じたことはありませんか?
この記事では、自宅練習用の音作りとバンドアンサンブルでの音作りの違いを徹底解説します。初心者ベーシストがつまずきやすいポイントも押さえつつ、実践的なコツを紹介します。
1. 家で弾く時の音作りの特徴
● 低音が出すぎる問題
ベース単体で音を作ると、どうしても低音を強調したくなります。特にアンプやオーディオインターフェースで練習していると、低音が豊かに響くセッティングが心地よく感じられるからです。
しかしこれは、バンドで合わせた時に他の楽器を埋もれさせる原因になります。
● クリアで目立つ音が好まれる
自宅練習では「弾いていて気持ちいい音」を追求しがちです。高域を持ち上げてアタック感を強調したり、コンプを強めにかけて粒をそろえたりする傾向もあります。
ただし、この音作りがそのままバンドで通用するとは限りません。
2. バンドで弾く時の音作りの特徴
● ミックスの中での役割を意識
バンドアンサンブルでは、ベースは「リズムとハーモニーを支える存在」です。ギターの中域やドラムのキックの低域との住み分けを意識する必要があります。
例えば、ギターがミドルを厚めに出している場合、ベースは中低域を中心に鳴らし、ぶつからない帯域を作ることが重要です。
● 抜ける音を意識する
「抜ける」とは大音量にすることではなく、他の楽器と重ならずに存在感を出せる音を意味します。
そのために、バンドでの音作りでは以下のポイントが大切です。
- ローカットで必要以上の低域を整理
- 中域(特に400Hz~800Hz)を少し持ち上げる
- スラップなら2kHz付近をブーストしてアタック感を強調
こうした調整により、バンドサウンドの中でベースが「聞こえる」音になります。
3. 家とバンドで音作りを切り替えるコツ
● イコライザー設定を分ける
自宅用とバンド用でEQのセッティングを分けてメモしておくと便利です。最近はマルチエフェクターやプリアンプにプリセットを保存できる機種も多く、切り替えが簡単です。
● 実際に録音して確認する
スタジオ練習を録音して聴き返すと、自分のベースがどうバンドに馴染んでいるか客観的に判断できます。自宅で良いと思った音も、録音で聴くと「抜けてない」ことが分かる場合が多いです。
● 音量バランスに注意
「音が聞こえない」と感じた時にボリュームを上げすぎると、全体のバランスが崩れます。まずはEQで周波数帯域を調整し、それでも足りない場合に音量を補うのが鉄則です。
4. まとめ
- 自宅練習音作り → 弾いて気持ちいい音(低音強め・高域クリア)
- バンド音作り → ミックスの中で抜ける音(中域重視・低音整理)
- コツ → EQの切り替え・録音チェック・音量よりも帯域バランス
ベーシストにとって音作りは永遠のテーマですが、「自宅での音」と「バンドでの音」は別物と割り切ることが大切です。これを意識するだけで、アンサンブル全体のまとまりが大きく変わりますよ。

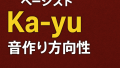
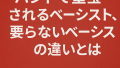
コメント