はじめに:ヘルツ(Hz)って何?
- 音の高さは「周波数(Hz=ヘルツ)」で表され、「A4(ラの音)」を基準に、そこから上下の音が決まるという仕組みです。
- 楽器をチューニングする際には、この基準となるA4の周波数をどこに設定するか(=“キャリブレーション”)が重要です。多くのチューナーは初期設定で 440 Hz にセットされています。
- しかし、現場やジャンル、共演楽器によっては、440 Hz以外(例:441 Hz、442 Hzなど)を基準にすることもあります。
では、「ペダルチューナーのメーカーによるヘルツの違い」とは具体的に何か? どう扱えばよいか? を段階的に見ていきましょう。
1. ペダルチューナーでの「ヘルツ(基準ピッチ)設定」の意味
1.1 キャリブレーション機能
ほとんどのペダルチューナーには、A = 440 Hz 以外の値へ調整できるキャリブレーション機能が備わっています。
例えば、BOSS TU-3では 436 Hz ~ 445 Hz まで可変という仕様が紹介されています。
この設定は、チューナーが「この基準音を“正しいA”として認識し、他の音を相対的に判断する」ためのものです。
1.2 メーカーによる初期設定の違い
メーカー/機種によって、初期設定のヘルツ(=デフォルトでどのHzに設定されているか)や、調整可能範囲・方式(ステップ単位、増減ボタン方式など)が異なります。
例:あるペダルは ±5 Hz の調整が可能、別のものは ±10 Hz または ±20 Hz という場合もあります。
また、ごく一部のモデルでは、表示に “何Hz” を直接出す機能を持つものもありますが、それはあまり一般的ではありません。
2. ヘルツを変えると何が変わるか?(音響的・実践的な差)
基準を 440 Hz から 441 Hz、442 Hz に変えると、実際にはどれほど違いが出るのでしょうか。
2.1 周波数差と聴感差
- 1 Hz の違いは、センチ(音程の単位)で言えば数セントにも満たない微細な差です。つまり、単独でギターを鳴らしただけではほとんど区別できないことが多いです。
- ただし、複数の楽器でアンサンブルを組むとき、基準Hzがずれていると倍音のズレで「和音の濁り」や「うまく調和しない感じ」が出ることがあります。特にレコーディング時やライブで他の楽器(ピアノ、管楽器など)と合わせる場合は注意が必要です。
2.2 弦への負荷、テンション変化
基準を高めに設定すると、音を高めに張る必要が出るため、弦のテンション(張力)が若干強くなります。これは楽器や弦への負荷が少し増える可能性があるため、無闇に極端な設定には注意が必要です。
2.3 実践的な選択の傾向
- ポップ/ロック系:一般的には 440 Hz を基準とするケースが多い
- セッション、ジャズ、現場ピアノと合わせる場合:441 Hz や 442 Hz を使うことも(ピアノがその基準で調律されている場合など)
- レコーディング:事前に全パートの基準を揃えることが重要。打ち込み音源は多くが 440 Hz 基準で設計されていることも多いため、揃えておくと安心。
3. メーカー別の注意点・傾向(例示)
以下は一例ですが、メーカー/機種を選ぶ際に「ヘルツ設定」に関して確認しておきたいポイントと傾向です。 メーカー/機種 キャリブレーション範囲/方式 特記事項・注意点 BOSS(例:TU-3) 約 436 Hz ~ 445 Hz に調整可能という報告あり 調整操作がモード+ボタン操作という方式。設定変更がやや煩雑なモデルも。 KORG 系 多くのモデルで基準ピッチ変更対応 ストロボモード搭載モデルなど高精度モード重視の傾向あり 小型・ミニペダル 機能を削って小型化している場合、キャリブレーション幅が狭い・非搭載のケースもある ヘルツ設定機能を重視するなら仕様をよく確認すること 高精度モデル/高級機 ±何十Hzまで、細かいステップで調整可能なタイプもある 表示精度やモード切り替え時の速度が鍵になることが多い
(※ 上記はあくまで一般的な傾向であり、各モデルの仕様を確認するのが確実です。)
4. 実際、どのヘルツを使えばよいか?選び方のガイド
4.1 バンドなら「メンバーで揃える」ことが最優先
他のメンバーがチューナーを使っている、またはピアノ/打ち込み音源と合わせるなら、まず基準Hzを揃えることが最も重要です。ズレていると、いくらチューナー上「正確」と出ていても実際には不協和音になります。
4.2 汎用性を重視するなら「440 Hz」をデフォルトに
特殊な指定がない限り、440 Hz を基準に使っていけば間違いありません。多くの現場・音源がこの基準で動いています。
4.3 より“響き”を意識したいなら、微妙な調整を試す
演奏ジャンル・楽器構成によっては 441 Hz や 442 Hz を使うケースもあります。ただし、1 Hz の差を聴き取れるかはかなり高度な耳を要することも多いです。特にレコーディングでは、変更による副作用(負荷、テンション変化など)も考慮する必要があります。
4.4 チューナーペダルを選ぶ際に確認すべきスペック
- キャリブレーション可能範囲(何 Hz ~ 何 Hz まで調整できるか)
- ステップ幅(1 Hz 単位か、2 Hz 単位かなど)
- 設定変更の容易さ(ボタン操作、モードの切り替え)
- 表示精度・反応速度(モード切替やノイズ耐性も含め)
- 高精度モード(ストロボ表示など)を備えているか
5. まとめ:ヘルツ設定の違いをどう扱うか
- 基本は 440 Hz で十分なケースが多い
- バンド/共演者との合わせ が最優先:Hzが違うと和音の濁りが出やすい
- ペダルごとにキャリブレーション機能を要確認
- 1 Hz の違いは感知が難しい ため、実戦での差異は限定的
- 高精度志向なら、表示精度・調整幅・モードの使い勝手重視
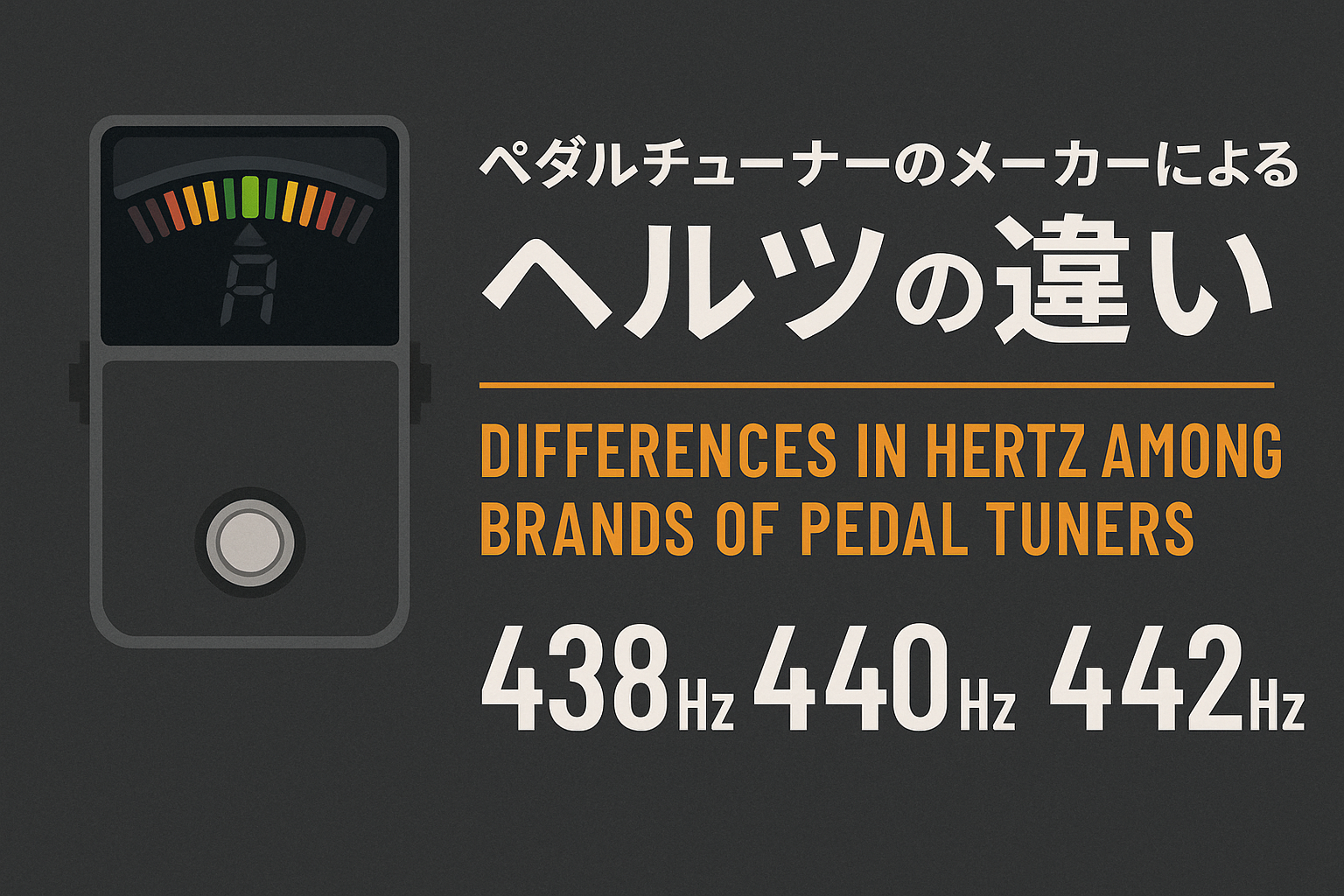
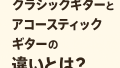

コメント